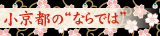山形市
戦国大名の最上義明が、五十七万石の城下町として整備したのが山形。
駅の近くにあり、今は博物館や郷土館のある霞城(かじょう)公園は明治維新までのお城だった。
ただし、藩として山形は江戸末期のころの石高はわずか五万石程度にまで落ち込んでいた。
古くからの特産は染料となる紅花で、これが京都へ送られ、西陣織りなどに使われて縁を深めた。
山形には近世の建物も残っており、ルネッサンス様式の文翔館(旧県庁舎・議事堂)、山形市郷土館、教育資料館が見所。特に、文翔館は重厚な雰囲気を持つ。
山形市郊外にあり、松尾芭蕉が「閑さや〜」と歌ったことでも知られる山寺(立石寺)は、慈覚大師により千百年前に創建されたもの。近くにはには山寺芭蕉記念館もあり、多くの観光客が訪れる。
石段を登り始めると、次第に移り変わる景色がある。
夏の五穀豊穣を願う田植え踊りから始まった「花笠まつり」は、東北を代表するお祭り。
冬になると蔵王の樹氷が見事だ。
現在の山形市では、霞城公園の本丸が復元工事中で、石垣の復元の工事中だ。
また、山形駅に隣接して新しく作られた二十四階立ての「霞城セントラル」には観光案内所がある他、展望台(無料)からは市内を一望することができる。
山形県の小京都・山形市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 名刹の「お寺」がある
地域情報
山形の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]yamagatamaru:10000059[/rakuten]
[rakuten]imayashop:10002468[/rakuten]
酒田市
江戸時代、酒田が北前船の港として栄えた歴史を持つのは、庄内地方が米の一大産地だったことによる。最上川の河口に港町だった酒田は、川村瑞賢が北前船の西回り航路を整備したことで、一気に江戸時代の主要港町に踊り出ることになり、それは「西の堺、東の酒田」と謳われたほどだ。
北前船による交易では、人や荷物の往来だけではなく、京文化も一緒に運ばれてきた。日本一の大地主として、藩主以上の力を持った豪商・本間家などが登場するのもそのころだ。井原西鶴の「日本永代蔵」に北国一の米商人として登場する鎧屋も実は酒田の商人。今はやや閑散とした雰囲気のある中心部だが、市内を歩くと随所に繁栄の跡を感じることができる。
また、当時の豪商が収集した文化財は、今では美術館などで公開されている。
港町としてのシンボルとなるのが、山居倉庫(さんきょそうこ)で、百年を経た今でも実際に使われているから驚く。
市内には港町の面影をあちらこちらに見ることができる。
六角灯台も自慢のひとつで、至る所で六角形をモチーフにしたモノを見かける。
「古寺巡礼」などで知られる写真家・土門拳の出身地でもあり、氏の業績を記念して作られた土門写真記念には遠方より訪れるファンも多い。
山形県の小京都・酒田市の観光ポイント
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
地域情報
酒田の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]yamagatamaru:10000775[/rakuten]
[rakuten]yamagatamaru:10000720[/rakuten]
湯沢市
秋田県の内陸部の南。冬は非常に雪深い土地で知られる。
銘酒の産地で、爛漫と両関の2大ブランドをはじめ、幾つもの造り酒屋が存在することから「東北の灘」とも呼ばれる。
いつも小京都を感じない湯沢だが、毎年8月に行われる「七夕絵どうろう祭り」の期間中は、小京都と呼ぶにふさわしい艶やかな夜になる。この美人画を絵どうろうに描いてを飾る行事が始まったのは江戸時代と伝えられ、秋田を治めていた佐竹藩の南家のあった湯沢に、京都の公家(鷹司家)から嫁いできたお姫様を、なぐさめるためだったといわれる。こうして、七夕の夜の湯沢は、素敵な明かりの灯る街並みに変身する。
湯沢市は他にも8月の「大名行列」、雪深い2月(旧正月)の「犬っこまつり」と伝統的なお祭りの多いことでも有名です。
郊外に目を向けると「川原毛地獄(植物のない硫黄の匂いに強い場所に三途の川渓谷などがあるが、実は鉱山の跡)」「泥湯温泉」、お湯の滝が落ちてくる「大湯滝」などが人気だ。
名水として知られる「力水」の泉が市役所の近くにあり、ポリ容器を手に、軽トラックなどに乗って汲みに来る人の姿が途切れない。
秋田県の小京都・湯沢市の観光ポイント
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
湯沢の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]umazakeya:10000141[/rakuten]
[rakuten]umazakeya:10000413[/rakuten]
角館
小京都と呼ばれる土地は多いが、その中でも知名度、人気なども含めてナンバーワンと言ってもいいほどの風情を今に残す角館。春は桜が、夏は新緑が、秋は武家屋敷の木々の紅葉が、冬は黒壁の塀に白い雪が、と四季を通じて美しい風景を見せてくれる。
角館は江戸時代に入ってから、佐竹家の北家の城下町であった。
町並みが京都のように南北に長く東西に短くなっているのは、初代藩主が公家出身のためだったことによる。さらに武家、商人の住む地域に別れて町割りが行われていた。二代目藩主の夫人もまた公家の出身であったため、徐々に京文化がもたらされたと伝えられる。
武家屋敷が幾つも並ぶ風景は、他の小京都にもないもので圧巻だ。
角館は武家屋敷と並んで桜の名所でもある。武家屋敷の塀に垂れるシダレザクラ、桧木内川沿いのソメイヨシノの桜並木は、ゴールデンウィークの時期に咲き、訪れる多くの観光客を魅了する。
解体新書の挿絵を描いた小野田直武、日本画家の平福穂庵、平福百穂親子の出身地でもあり、記念美術館もある。
山桜の皮を利用した樺細工、カエデの若木でカゴや小さな馬の姿を作るイタヤ細工が伝統的な特産品だ。秋田新幹線(盛岡からはミニタイプの高架を走らない新幹線だが)が開業してからは、駅前を中心にずいぶんと整備された感がある。秋田内陸縦貫鉄道も角館駅が始発駅。
秋田県の小京都・角館町の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
秋田県 角館町観光協会 Kakunodate Tourist Association
角館の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]seibidou:10031634[/rakuten]
[rakuten]hyakunote:10000216[/rakuten]
岩出山町
戦国時代の奥羽の覇者・伊達政宗が、その後の拠点となる仙台青葉山城へ入る前の十二年間を過ごしたのが岩出山。宮城県の内陸北部にあり、先の鳴子温泉を越えると秋田・山形の両県境はもうすぐだ。戦国時代にあって、京の都に上り、天下に号令するのに岩出山の位置は距離的にあまりにも遠すぎ、政宗も若すぎた。岩出山城跡は公園になっており、仙台市の青葉城跡にある伊達政宗像とは違う白い像が、かつての城下を見下ろしている。伊達政宗を偲んで始まった「政宗公まつり」は、今年で41回を数える。
岩出山の領地は、江戸時代になると仙台に居城を構えた政宗に変わって、4男の宗泰が継ぐ。そして、京都の冷泉家からの二代にわたるお輿入れにより、和歌や能などの京文化が岩出山に伝えられた。
江戸時代には、松尾芭蕉もこの地に足を運んで詩を詠んでいる。
町内には内川遊歩道として散策路になっている「学問の道」に沿って水路が流れているが、元々は伊達政宗が用水路として整備したもの(現在のものとは形が変わってはいるが)。
戊辰戦争おいて仙台の伊達藩とともに幕府側にあったため、明治時代には石高を大幅に削減され、多くの家臣が新天地を求めて北海道へ渡った。今も北海道に「伊達」縁の地名が残るのは、岩出山から続く明治初期の苦闘の歴史があったためだ。
なお、かりんとうが名物で、町内の店頭で、大きなアルミの缶に入って並べられている姿に驚く。最近、市内の通りがきれいに整備され、新しくできたポケットパークには、松尾芭蕉像も移ってきた。
宮城県の小京都・岩出山町の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 政宗公まつり
地域情報
岩出山の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]shiogamagyoko-uomi:10000085[/rakuten]
村田町
小京都の中でも「蔵の町」として知られる村田町は、モータスポーツファンにとっては鈴鹿サーキットと並ぶ聖地でもある。スポーツランドSUGOの中にある国際格式のコースでは、ヤマハ発動機系列のサーキットとして誕生したコースでは数々の国際大会が開催され、語り継がれる名勝負もある。
歴史的は伊達政宗の時代以前より伊達家と縁が深く、同家の家臣の小山九郎業朝によって初めて村田のお城が築かれた。
江戸時代に入って商業で栄えたのは、山形と宮城を結ぶ街道の要所にあり、特に紅花の取引によるものが大きい。当時は市も開かれ活発に取引が行われていた。村田に集められた紅花は関西からの品質に対する評価が高く、京都や大阪、又は江戸に送られた。
村田商人はこの紅花の取引によって財を成したことで知られ、当時の豪商の名残として、町内の通りには蔵が残っている。
観光客を意識していない分(現在も住居となっているため公開していない)だけ情緒が保たれている。
土蔵作りの町並みの他の見所としては、伊達家の菩提寺である龍島院にある京都の詩仙堂を模した池泉観賞式の庭園が美しい。
なお、小京都にちなんで「小京都むらたフォトコンテスト」が行われている。
郊外には谷山温泉が名高い。
宮城県の小京都・村田町の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 江戸時代からの「蔵」を見ることができる
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
地域情報
村田の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]toukoku:10000013[/rakuten]
水沢市
岩手県中央部にあり盛岡市の南に位置する。市内には同じ小京都の盛岡市から流れてきた北上川がある。
南部鉄器のふるさとで、現在も多くの工房がある。
市内を歩けば南部鉄器を利用した公共物(橋の高欄や街路灯など)やモニュメントを見ることができるのもそのためだ。
「水沢市伝統産業会館(キューポラ館)」では南部鉄器の製作過程や歴史を学べる。
岩手県で一番小さな市ながら、時代を築いた偉人を生んでおり、高野長英(幕末の蘭学者でシーボルトの弟子)、後藤新平(内務大臣)、斉藤實(2.26事件で暗殺された当時の首相)の記念館がそれぞれあり、遺品などが保存・公開されている。
水沢の歴史は古く坂上田村麻呂により造営された鎮守府があり、胆沢城跡として発掘されている。
ここでは、酋長であったアテルイとの攻防戦の地して今日に語り伝えられる。
江戸時代は伊達一門の留守家一万六千石の城下町となり、こちらは武家屋敷が残っている。
殿様が江戸を訪れたときに火事の多さに驚いたところから始まった「日高火防祭」は四月の末に行われる防災をテーマにした珍しいもの。
水沢公園は桜とツツジ祭りで賑わう市民の憩いの場所。
岩手県の小京都・水沢(奥州市)の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 名刹の「お寺」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
水沢の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]manryo:10002571[/rakuten]
[rakuten]kenko-academy:10051881[/rakuten]
遠野
柳田国男の「遠野物語」の舞台となった土地として、誰もが一度は聞いたことがある地名ではないだろうか。
カッパ、ザシキワラシ、オシラサマ、雪女…。
遠野物語は、遠野出身の佐々木喜善が語った遠野に伝わる多くに民話に興味を持った柳田が、明治末期にまとめあげたものだ。
この著作によって民間伝承は民俗学までに引き上げることになった。
民話の故郷へ向かうには、東北新幹線の停車駅や空港がある花巻から乗り換えて岩手県の山々に囲まれた内陸部に入る。遠野物語では「花巻より十余里の路上に町場三ヶ所あり」と紹介されている。当時は足を運ぶのも困難な土地であったようだ。
物語に登場するカッパ淵、キツネの関所などを思い浮かべると、途中の景色も何となく不気味な雰囲気を感じてしまうのも不思議なものだ。
昔話の伝承者である語り部による方言が豊かな昔語りは、今も伝承されており、観光客でも「とおの昔話村」などで聞くことができる。
今は古参道跡しか残っていないが、遠野物語にも登場する信仰の山、早池峰山にも時間があったら登ってみたい。
同じような東北の風景の中でも「ここだけは別のような気がする」のは、やはり遠野物語の影響だろう。
岩手県の小京都・遠野市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
遠野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]joyport:10001858[/rakuten]
[rakuten]auc-michinoku-f:10000044[/rakuten]
盛岡市
宮沢賢治の作品の中で、イーハトーブ市又はモリーオ市として登場するのが北東北の中心に位置し、東北新幹線が八戸まで延伸する前は終着駅だった盛岡。
盆地のため、夏は暑く冬は寒い気候は京都に似る。
市内で中津川、雫石川、北上川の三川が合流して南へ向かう。
西に見えるのは賢治も登っている(何度も)岩手山。
江戸時代は南部藩二十万石の城下町として整備され、今でも市内の細い道の間に、当時の面影を感じることができる。お城のあった盛岡城跡は岩手公園となっているが天守閣はなし。ただ、岩手の花崗岩で造られた石垣が残っている。近代に入ってからは原敬などの偉人を輩出しており、先人の偉業を紹介している記念館もある。
市内を散策すると、江戸時代から明治時代にかけての歴史的建造物や、彫刻が歩道にあったりして楽しい。また、金田一京助、石川啄木、宮沢賢治など文化人との縁の地であるため、文学碑や歌碑、記念するブロンズ彫刻と出会うことになる。
歩くときは、テーマを持って散策するとより楽しいだろう。
美術館も多い街だ。
食の分野では、わんこそば(美味しいとは思わないが)や冷麺、南部せんべいが名物。
お祭りでは、夏の「盛岡さんさ踊り」が東北三大祭りに数えられている。
岩手県の小京都・盛岡市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 名刹の「お寺」がある
地域情報
盛岡の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]todakyu:10000276[/rakuten]
[rakuten]iwate2:10000087[/rakuten]
弘前市
戦国時代にこの一帯を平定した津軽氏の流れは江戸時代にも続き、十万石の城下町として現在の青森県の中心となった。
市内には岩木川が流れ、岩木山の麓には名物のリンゴ畑を見ることができる城下町だ。特に岩木山周辺の高台から眺めるリンゴ畑の姿は美しい。
ゴールデンウィークの頃に桜が満開になる弘前公園は日本有数の規模で、大勢の観光客で賑わう。特に天守閣を背景にした花見の様子は、この季節になると繰り返しテレビニュースで放送されるので、記憶にある方も多いのでは。
夏には七夕行事が「弘前ねぷた」が市内を歩く。知名度は青森ねぶたに一歩譲るが、扇形の山車の持つ情緒や優雅さがあり、しかも安心して見ることができる。
新緑の夏、紅葉の秋に続いて、雪の降り積もる2月になると、雪灯籠まつりが始まる。雪の灯籠が並び夜になると明かりが灯される姿は幻想的だ。会場となる弘前公園は、市内の中心にあることもあって四季を通じて人々を魅了する。
本州最北の小京都でもある弘前は、お城跡や武家屋敷、寺院に江戸期の歴史を感じさせながらも明治から昭和初期にかけてのルネッサンス調の建築物も幾つも残っている。
太宰治をはじめとする文豪による作品の舞台にもなっており、文化的な側面も持つ都市でる。
青森県の小京都・弘前市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
地域情報
弘前の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]kenko-academy:10063900[/rakuten]
[rakuten]hashimotoya:10000539[/rakuten]