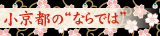金沢市
市内の随所に加賀百万石の面影の残る金沢は、歴史的にも規模的にも、そして文化的にも小京都の中でも最大級である。歴代藩主が工芸などに力を入れたところから、市内の随所に、深く文化を感じさせるものがある。
四季を通じて様々な表情を持った風景も楽しむことができ、その代表がかつて栄華を偲ばせる兼六園だ。歴史的には豊臣秀吉の信頼の厚かった前田利家が戦国時代の末期に金沢に入ってから城下の整備は早いスピードで進んだ。それ以前は、織田信長の配下であった佐久間家が整備をしている。かつては、歴史的にも画期的な、一向一揆の自治共和国があった土地でもある。
現在の金沢は、古い街並みと伝統文化、近代的な高い建築物が共存している。
特産品は加賀友禅、金箔などをはじめ、漆器、大樋焼、九谷焼など多数。
庭園の美で知られる兼六園を始め、寺院、博物館、資料館などの見所も多い。とても一度の旅行だけでは見ることができない、たくさんの魅力が詰まった北陸一の都市だ。
NHK大河ドラマ「利家とまつ〜加賀百万石物語〜」の放送に合わせて、金沢城跡地で『加賀百万石博』が開催された。
石川県の小京都・金沢市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 江戸時代からの「城下町」
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 江戸時代からの「蔵」が見ることができる
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 江町人文化が息づく
地域情報
金沢の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]miyage:10006030[/rakuten]
[rakuten]konchikitai:10000211[/rakuten]
城端町
「じょうはな」と読む。
五箇山の山すそに栄えたお寺と、華麗な曳山を持った町だ。戦国時代には一向一揆の北陸の拠点として織田信長を苦しめたこともある。やがて江戸時代になると、絹の生産により町は賑わうようになる。
城端神明宮の春季祭礼である曳山祭は三百年前から続くもので、「江戸」らしい屋台が練り歩く。お祭りでは平家の落人が唄い踊ったのが始まりと伝えられる「城端むぎや節」もある。
城端は、坂の町でもあり、それぞれの坂に名前がある。「ぼたもち坂」「地獄谷の坂」「兵舎の坂」、「御坊坂」といった具合だ。
一番の見所になる城端別院善徳寺は、1559年に蓮如上人が城端へ移住してきたことによる。築五百年を越える建物で、随所に各時代の特徴を持った建築様式を見ることができる。同じ敷地の中には宝物館もあって見学で可能だ。
水量の豊かな城端を歩くと、幾つもの水車と出会う。それもからくりなどの手の込んだものが多く、「水車ウォッチングロード」と呼ばれる道は不思議な散歩道となる。道路沿いの水路の上に趣向を凝らした水車が点在する。交通安全などのテーマを持ったものある。また、個人宅でのかなり凝った水車が玄関先にあったりする。
高岡から各駅停車の列車に揺られて降りた城端駅は、冬には雪深い終着駅でもある。
また、城端には水芭蕉の生息地として有名な「縄ヶ池」もある。
富山県の小京都・城端町の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
城端の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]kirakuya-kawai:10000145[/rakuten]
[rakuten]takazmi:10000341[/rakuten]
加茂市
新潟県の内陸部中央にあり、京都とゆかりの地名を持つ。三方を山に囲まれた盆地で、桐タンスの生産ではシェア日本一を誇る。冬の寒さは厳しいが、寒椿の名所だ。一番の見所は小京都の由来にもなっている青梅神社で、公園と一緒に整備されている。元々は青梅首(おうみのおびと)が創建した神社だが、平安京遷都のときに、青梅神社が京都加茂神社の社領になったことから加茂の地名がついた。
市内を流れる川の名も加茂川。
加茂駅から商店街を通じる道は「ながいきストリート」と呼ばれる。つまり、ぶらい歩いて買い物をすれば健康になり「ながいきながいき」、といったところか。加茂川に等間隔で掛かる八つの橋の親柱はそれぞれ違うもので、中でも葵橋が京都の雰囲気に近い。駅前から橋を対岸へ渡ったり戻ったりして見学できる。
群生地があることで知られる「ユキツバキ」は加茂市の花となっており、毎年四月中旬から下旬に「雪椿まつり」開催され、加茂山公園の一帯で市民茶会などのイベントが続く。
新潟県の小京都・加茂市の観光ポイント
- 京都ゆかりの「寺院」がある
地域情報
加茂の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]coueido:10000197[/rakuten]
[rakuten]kiritansu:10000241[/rakuten]
湯河原町
神奈川県第二の温泉郷(一番は箱根。ちなみにお隣の温海は静岡県になる)として栄える観光の町。首都圏からも近いため、温泉を求めて多くの観光客が訪れる。温泉の歴史は、奈良時代の万葉集にも湯河原温泉が歌われていることからかなり古く、鎌倉時代の源氏軍から日清戦争、日露戦争まで、常に負傷した兵士の治療の場でもあった歴史がある。矢で負傷した「たぬき」が温泉を発見したという伝説もあるため(湯河原駅の中にはたぬきの像もある)怪我の治療の場のようなイメージがあるが、戦後は新婚旅行の地となった時代もあった。
多くの文豪や画家が湯河原に逗留したため、それに関連の作品を残しており資料も多い。
文化14年(1817年)光格天皇による院政が開かれたときに、京都仙洞(せんとう)御所の州浜(すはま)に吉浜海岸(現在は湯河原海岸と呼ばれているが、町名には吉浜の名前が残っている)の石が献上された。この石は、なんと石一個が米一升と同等に交換されていたことから、「一升石」と呼ばれて、京都へは2千俵もの石が運ばれたといわれている。これが小京都の由来だが、全国小京都会議で小京都に認定されたことを記念して、駅前にポケットパークが作られている。
神奈川県の小京都・湯河原町の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 町人文化が息づく
地域情報
湯河原の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]ringbellshop:10000113[/rakuten]
[rakuten]mediaprice:10023006[/rakuten]
嵐山町
歴史的に京と結びつきの深い小京都の中にあって、風景が似ていることから小京都になっているのが嵐山。京都の「あらしやま」に対して「らんざん」と読む。日本最初の林学博士で日比谷公園などを設計した本多静六博士が、槻川の渓谷を「京都の嵐山に似ている」と評したのが町名の由来になる。
比企丘陵の中枢部のあり、自然に富んだ地形の中にある嵐山町は、縄文・弥生・奈良・平安・鎌倉・室町・戦国と各時代の遺跡が出土している歴史の町でもある。特に平安から鎌倉時代にかけては、木曽義仲や畠山重忠などの板東武者の出身地であり、館跡が残っている。現在は埼玉県立歴史資料館となっているのは「菅谷館跡」で、中世城郭の原型を見ることができる。
かつては、上野国と武蔵国を結ぶ古道で、通称「鎌倉街道」が通っていた場所であり地上交通路の要所であった。鎌倉街道も跡を見ることができる。秋には、板東武者ををにちなんで、時代まつりが行われている。
国蝶オオムラサキが多数、生息する地としても知られている。小京都の所以ともなっている武蔵嵐山渓谷周辺樹林地が、トラスト保全されるなど自然保護にも力を入れている。
埼玉県の小京都・嵐山町の観光ポイント
- 京都の嵐山を彷彿とさせる風景
地域情報
埼玉の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]saitama-bussan:10000105[/rakuten]
小川町
外秩父山系に山々に囲まれた地方都市だが、盆地の中を流れる槻川が京都の姿は京都を彷彿させているのかもしれない。歴史のある町らしく神社仏閣が多い町だ。
特産品は小川手すき和紙で、起源は千二百年とも千三百年前ともいわれている。江戸幕府の設立の伴い、事務手続きに大量の紙が必要となり、距離的に江戸に近い小川町は一大産地に発展する。現在も和紙の生産は続けられており、無形重要文化財にもなっている。
清らかな水のためか、伝統工芸としては水嚢(すいのう)、絹織物、建具、鬼瓦などでも著名な土地。これらの伝統工芸は「埼玉伝統工芸会館」で、展示だけではなく製作工程を見学できるほか、埼玉県内の伝統的手工芸品の数々の職人の技を学ぶことができる。その種類は、雛人形、足袋、釣り竿、羽子板、ダルマ、鬼瓦、染め物と多岐にわたり、体験コーナーや実演もある。
小川町と縁のある明治時代の山岡鉄舟が、小川町の料理人の忠七へ「料理に禅を盛れ」と注文して作られた「忠七めし」は、今も人気のメニュー。
カタクリとオオムラサキの里としても有名。
小京都にちなんで「小京都おがわを描く展」インターネットギャラリーが開催されている。
埼玉県の小京都・小川町の観光ポイント
- 和紙のふるさと
地域情報
小川の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]saitama-bussan:10000295[/rakuten]
[rakuten]saitama-bussan:10000292[/rakuten]
佐野市
昔は佐野厄除大師のある町として知られ、厄払いの参拝客でたいへんな人出となる佐野であったが、最近ではラーメンの町として知名度が急上昇中である。佐野ラーメンは、湿度のある気候と天然のわき水、そして青竹打ちのよって腰の強い麺により、独自の味とコクのあるラーメンである。以前から件数の多かったラーメン店が、周辺のゴルフ場へやって来るゴルファーの口コミで広がったのがブームの始まりといわれている。事実、うまいラーメンが多い。市内を散策していると、食事時ではない時間帯なのに、突然長い行列を遭遇することがある。これはラーメン目当てにやって来る観光客の姿だ。
今ではラーメンの町となった佐野の歴史は意外と古く、三毳山が万葉集に詠われている。それを記念して、万葉自然公園かたくりの里が郊外に整備されている。また、栃木と同じように例幣使街の宿場町でもあった。日光東照宮を造営した職人が佐野に住み着いたことにより、武者絵や掛軸などの画工が特産になった。
江戸時代は彦根藩領となり、幕末の大老であった井伊直弼の墓も市内の天応寺にある。近代では、産業振興を急ぐ明治時代に起きた足尾鉱毒問題の解決のために尽力した田中正造の出身地でもあり、佐野市郷土博物館に展示されている他、生家が保存されている。京都を真似て三毳山(みかもやま)では大文字焼きが行われている。
最近では、郊外に誕生した巨大アウトレットが話題になっている。
栃木県の小京都・佐野市の観光ポイント
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
佐野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]orudo:10002065[/rakuten]
[rakuten]trv:10004453[/rakuten]
足利市
足利は、栃木や佐野と同じように両毛線沿いにある「関東の小京都」は歴史の街であり、地名からもわかるように室町幕府の将軍家「足利」家の発祥の地として有名。足利は鎌倉時代から続く名門だったが、弱体化した鎌倉幕府を倒した後、南北朝時代を経て開府した。
日本最古の学校である足利学校がこの地に設立された時期については諸説があり、平安時代とも鎌倉時代ともいわれているが、室町時代には関東管領の上杉憲実が整備し、全国から学徒を集めた。多いときには全国から三千人の学生が集まっていたといわれ、多くに優秀な人材を輩出したと伝えられる。その名声は、宣教師ザビエルによってヨーロッパにまで届いたほどだった。
時代は移り、江戸時代になると学校の性格は変わったが、その学問の歴史は受け継がれ、やがて文化的施設として近代を向かえる(なお、復元された足利学校の建物は江戸時代の絵図を参考にしたもの)。
歴史的な建造物としては、尊氏誕生の地があり足利一門の氏寺「鑁阿寺(ばんなじ)」が歴史を感じさせる。
足利は、織物、染物が盛んであり、伝統的な特産品としては千二百年の歴史を持つ足利織物、美術館も多い。
市内を流れるのは渡良瀬川で、森高千里の歌にある渡瀬橋も実際にある。
栃木県の小京都・足利市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
地域情報
足利の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]genkiseikatushop:10000456[/rakuten]
[rakuten]enhancial:10000166[/rakuten]
栃木市
徳川家康を祭った日光東照宮へ朝廷から幣帛を奉納するため勅使が通った道を例幣使街道(れいへいしかいどう)という。江戸末期の栃木市は、その使者らの宿場町であった。元々は城下町だが、巴波川(うずまがわ)の水運を利用して栄え、商人の町としての色彩を次第に濃くした。当時の土蔵や屋敷の黒板塀は、今も映画ロケのセットのように並んでいる。蔵屋敷のある川沿いには江戸の雰囲気を持つ風景を保っており、この周辺は観光客の散策路となっている。巴波川も木製の資材を利用し、美しい川に整備されている。
作家の山本有三は、この栃木で生まれ幼少の頃まで過ごしており、氏の業績を記念して「山本有三ふるさと記念館」もある。
栃木を代表するお祭りは山車が練り歩く「栃木秋まつり」だが、五年に一度しかやってこない。そのため、大きな電気仕掛けで動く山車が展示されているのが「とちぎ山車会館」で、新しい観光施設だ。
今でこそ県庁は宇都宮市にあるが、以前は栃木にあり、旧県庁の木造洋館は市役所別館として今も使われている。この別館はモスグリーン調の色彩が美しい。
また、栃木は下駄の産地でもある。
栃木県の小京都・栃木市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 江戸時代からの「蔵」が見ることができる
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
地域情報
栃木の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]gs:10002928[/rakuten]
[rakuten]trv:10004451[/rakuten]
古河市
地名からもわかるように、利根川と渡良瀬川の河川交通の要所として栄えた歴史を持つ。
古には万葉集の歌の中に「船渡し」があったことが記されており、記念碑が古河駅前に立っている。
江戸時代には奥州街道・日光街道の宿場町となり、特に将軍家が日光東照宮参拝時の宿泊場所でもあった。
江戸時代を通じて藩主は何度も交代しているが、関東の要所であったためか、いずれも譜代大名が充てられている。その歴代の中でも土井利位は、徳川幕府での老中職にあった他、雪の結晶の研究家としても知られ、冬に雪片を集めて顕微鏡により結晶を観察した成果は「雪華図説」に著されている。
市内には雪の結晶をシンボルにしたマークを各所で見ることができる。
家老職にあった鷹見泉石(たかみせんせき)は、西洋に関する多くの研究の第一人者で、「新訳和蘭国全図」は一国の地図を日本人の手のよって作られた初めてのもの。
古河藩は江戸時代の中において、すでに世界に視野を広げており、これらは古河歴史資料館に資料が残っている。
お城跡には天守閣などは残っていないが、武家屋敷は前出の「鷹見泉石邸」が見学できる。
明治時代には製糸業が盛んになり「糸の町」として発展を遂げ近代を向かえた。
茨城県の小京都・古河市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷(跡)」が残る
地域情報
古河の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]auc-kanekorice:10001888[/rakuten]
[rakuten]sakeyasui:10000036[/rakuten]