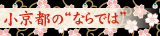出石町
出石城は、関ヶ原の合戦の直後に城主となった小出吉英により築城されたもの。小出家は断絶となった後は松平家、仙石家が江戸時代を通じて治めた。天守閣は元々ないが、隅櫓が復元されている他、藩政時代を偲んで大名行列のイベントが行われている。
江戸時代の家老屋敷が保存・公開されているのが特に興味深い。なにしろ、出石は日本三大お家騒動のひとつで、藩主の親戚筋にあたる有力者同士(名字も同じ仙石氏)が財政運営を巡って争ったのが発端になった「仙石騒動」が勃発した土地。屋敷の中には秘密の二階があり、刀を振り回せないように天井を低くし、屋根への出入口もある。さらに一階では階段を隠すと平屋のように見えるのである。家老屋敷ながら忍者屋敷風で、当時の二大勢力による切迫した空気が伝わって来るかのようだ。
なお、このお家騒動は幕府の知るところとなり、出石藩は石高を大幅(半分強の三万石)に減らされる。騒動の代償はとても大きかった。(取り潰しにならなかっただけよかったのかもしれないが。)
出石のシンボルは辰鼓楼(しんころう)と呼ばれるかつての木造の塔で、江戸時代には登城を藩士に伝えるための太鼓があり、三の丸付近にあったもの。明治時代に太鼓の代わりに大きな時計が取り付けられており、町内では一番人気の観光スポットとなっている。碁盤の目状になっている旧城下町を歩けば、当時の面影を見ることができる。
蕎麦が約三百年も続く出石の名物だが、最近は蕎麦(特に名物はさら蕎麦)を利用して観光誘致も行われている。確かに出石のさら蕎麦は美味だ。また、沢庵漬けを発明した沢庵和尚も出石の出身で、縁の宋鏡寺(すきょうじ)は沢庵寺とも呼ばれている。
なお、出石は古い歴史を持ち、古事記、日本書紀にも地名が登場している。
兵庫県の小京都・出石町の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
出石の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]sato:10014470[/rakuten]
[rakuten]yakusou:10014568[/rakuten]
伊賀上野
伊賀忍者と松尾芭蕉の故郷、伊賀上野。おかしな取り合わせだが、俳句と忍者が伊賀上野の特色で、芭蕉は諸国を訪ねたため、松尾芭蕉忍者説までも存在する。荒木又右衛門の決闘した「鍵屋の辻」もこの伊賀上野にある。
駅前には松尾芭蕉の像が立ち、市内には生家、記念館、芭蕉の生誕三百年を記念して作られた俳聖殿の縁の建物がある。
忍者の里としては、忍者屋敷もあるが、かなり観光色の強いものだ。観光名所には忍者の扮装をした切符売りのおばさん、観光案内所の女性、駐車場整理のおじさんもそうだ。市議会議員全員が忍者の扮装で議会を開催してニュースに取り上げられたこともある。
菅原神社の秋祭りとして、だんじりと鬼行列がある。だんじりの山車はだんじり会館で見ることができる。この山車あたりが小京都らしい。
現在の伊賀上野城は本物の石垣の上に、復元の天守閣を造ったもので、本来の姿とは違う形になっている。普請の名手と言われた藤堂高虎が造らせたたもので、鋭い角度の石垣が素晴らしく、黒澤明監督作品の映画・影武者のロケ地にもなっている。江戸時代の初期に改修した理由は、豊臣秀吉没後覇権を狙って徳川家康が大坂を包囲(篠山城、和歌山城、彦根城などと)するように整備させた。また、大坂夏の陣で破れたときの籠城用の意味もあり、場内では深く掘られた井戸を見ることができる。
三重県の小京都・伊賀上野(上野市)の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
伊賀上野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]greengrass:10216726[/rakuten]
[rakuten]kimonoichiba6:10118037[/rakuten]
西尾市
鍵万燈と呼ばれる旧盆に薪を鍵状に連ねて燃やす行事は、京都の大文字焼きを真似たのが始まりだと伝えられている。
駅前を流れるみどり川には、京都風に二条から四条と名づけられた橋が架かっている。
抹茶の産地でもある。
重厚な雰囲気を持つお寺、短いながらも昔の面影を残す「順海の路地」と呼ばれる通りがある。
承久の乱での功績のより足利義氏が守護となり、西尾城の前身である西条城を築城したのが城下町の始まりと伝えられる。関ヶ原の合戦後、本多康俊が藩主として入城、その後、藩主は、松平、本多、太田、井伊、増山、土井、三浦と、いずれも譜代大名の間で何度も交代している。中でも六万石に加増となったのは、代々幕府の要職を務めた松平家になってから。天守閣をはじめとするお城は明治維新に際して取り壊された。今は公園となり、本丸丑寅櫓(ほんまるうしとらやぐら)、鍮石門(ちゅうじゃくもん)が復元されている。変わっているのは、西尾城は天守閣が本丸ではなく二の丸にあった。
縄文時代の遺跡である八王子貝塚があることでも知られている。
愛知県の小京都・西尾市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
西尾の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]apita:10074082[/rakuten]
[rakuten]tokiwadrug:10009050[/rakuten]
郡上八幡
澄みきった水と徹夜で踊るまくる「郡上おどり」で知られる城下町・郡上八幡は、長良川の上流に位置し、特に名水の町として知られる。町を歩き、生活用水として使われている場に出会いと、誰もが水の恩恵について再発見するだろう。
この地に八幡城を築いたのは江戸初期に藩主となった遠藤慶隆で、このころから無礼講の踊りが行われ、今の郡上踊りの原点となった。その後の藩主は譜代大名が入れ替わって治めて明治を迎えている。今ある天守閣は、昭和に復元されたコンクリートのお城だが、郡上八幡のシンボル的な存在になっている。天守閣から見える山々に囲まれた八幡の町はとても美しい。
時代は遡るが、応仁の乱を避けてこの地へやってきた連歌師の宗祇は、清水のそばに草庵を結んだ。このことから、今もこの近くにある清水は宗祇水と呼ばれ、多くの観光客が訪れる。また、この清水は名水百選の一号でもある。
山間の小さな町のため、高速道路ができるまでは交通の便もよくなかったであろうが、その分、古い町並みが残っている。その魅力は小京都の中でも五本の指に入る。
岐阜県の小京都・郡上八幡の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 町人文化が息づく
地域情報
郡上八幡の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]apita:10019541[/rakuten]
[rakuten]m-suteki:10076763[/rakuten]
高山市
名古屋と富山の間、日本列島の中心部にも思える山深い地に高山盆地がある。
豊臣時代より大野越前を整備した金森長近が高山に入り江戸時代を迎えた。この間に、高山に街並みも整備されたといわれる。金森家が六代続いた後に天領となり、幕府が直轄するようになる。その間には、財政難の幕府の増収政策により年貢が重くなったため農民一揆も続発した歴史もあった。当時、江戸から郡代がやってきて行政を納めた高山陣屋が今も残っており見学も出来る。
豪華な屋台が歩く高山祭は、日枝神社の春の高山祭、桜山八幡宮秋のふたつがある。高山祭りでは、山車に乗ったからくり人形が演ずる。
戦災を免れた高山には、古くからの街並みや寺院が残る。特に「古い町並み」と呼ばれる商人街であった場所は、綺麗な町並みが保存されている。
郊外には、まつりの森や飛騨の里などの新しい観光施設が誕生している。特に飛騨地方の民家三十余棟を移設して集めた「飛騨の里」は迫力満点。観光シーズン以外でも観光客が多い小京都だ。
飛騨春慶、一位一刀彫が技。飛騨そば、飛騨ラーメン、飛騨牛、みたらしだんごなどが名物。
岐阜県の小京都・高山市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 江戸時代からの「蔵」が見ることができる
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
高山の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]bigbe2:10007197[/rakuten]
[rakuten]avance-etigo:10000334[/rakuten]
飯田市
長野県の南部。南アルプスと中央アルプスを眺望し、諏訪湖から流れる天竜川が市内を流れる。
市街地の中心部を横断するのは、飯田の特産りんごにちなんだ「りんご並木」。並木通りのある都市は多いが、飯田では幅の広い緑地帯にリンゴの木が市街地を横断している。かつて飯田市は大火によって市街地の4分の3を消失した経験を持ち、その教訓から作られた防火帯が、長いリンゴ並木になっている。市街地が碁盤の目状に整備されたのもこの大火の後。
江戸時代は小笠原家と飯田を整備した脇坂家が藩主だが、戦国時代は武田信玄の支配下にあった。
飯田には三百年の歴史を持つ黒田人形に代表される人形芝居、人形浄瑠璃が今に伝わる町でもある。最近では伝統的な人形劇をさらに発展させ、「人形劇の街」として人形劇として売り出し中。特に世界と日本の各地から人形劇を一堂に会するイベント「人形劇フェスタ」が好評を博している。
飯田市内からは相当な距離と細く曲がりくねった道であるためか、ガイドブックに紹介されていないこともあるが、面白いのが「太平宿」。かつて街道に、昔ながらの建物を移設保存している。
長野県の小京都・飯田市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
飯田の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]giocraft:10000443[/rakuten]
[rakuten]doremi:10065683[/rakuten]
飯山市
信州らしい山のある風景の中、千曲川の近くに二十二の寺社があるため寺の町と呼ばれる。なんとJR飯山駅のホーム上にも鐘があるほどだ。各寺院には統一された案内板が設置されているので、地図を持たなくとも寺院巡りをすることが出来る。中でも著名なのが名僧慧端が修行した「正寿庵」、島崎藤村の破壊のモデルになった「真宗寺」、歴代藩主の菩提寺でもある「忠恩寺」。
飯山駅と北飯山駅の中間にある国道292沿いでは、きれいなアーケードにより通りが整備されている。
飯山仏壇、内山紙が伝統的な工芸として受け継がれている。また、スキーやパソコンモニタの有名製造会社もあり、足を伸ばせば名湯も近い。
城下町としての飯山の歴史は、戦国時代の名将・上杉謙信が武田信玄と何度も覇権を争った川中島合戦の拠点するためにお城を築いた場所。そして、お城を中心とした町作りがスタートした。飯山城跡は公園になっているが、門が復元され、お城風の武道館などが建っている。
お祭りとしては、いいやま雪まつり、いいやま菜の花まつり、など。小京都らしく、大文字焼きの行事が八月に行われる。
長野県の小京都・飯山市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
地域情報
飯山の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]gifutoman:10000049[/rakuten]
[rakuten]shinsyu-hearts:10000047[/rakuten]
松本市
長野県の中心部であり地理的には本州中央部に位置する城下町。見所はなんといっても国宝の松本城だ。その規模と黒壁の美しさは、他に類をみない。松本は街道が交差する要所であったため、松本城も戦闘を考えての造りになっている。関ヶ原の合戦の十年前から石川数正・康長親子により築城が始まったもので、すでに築城されてから四百年を経過している。天守閣も素晴らしいが、月見櫓も同様に美しい。
遠くには、日本の屋根「北アルプス」も眺めることができる。お城の近くのは、旧開智学校や松本旧司祭館などの近代以降の西洋建築も現存しており、松本城の近くにあるので一緒に見学できる。
松本のもうひとつの美しい伝統は蔵で、今も商店、飲食店、旅館、さらにカラオケ店としても利用されている。また、伝統工芸で有名な松本民芸家具や松本紬などの技術も継承されている。
日本民族資料館やはかり資料館、アルプス山岳館、日本浮世絵博物館、日本司法博物館などのユニークなミュージアムがあるのも松本の特徴。さらに足を伸ばせば湯量の豊かな大小の温泉郷が点在する。特産としては、信州そば、松本手まり、松本民芸家具など。
長野県の小京都・松本市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」(国宝天守閣もある)
- 名刹の「お寺」がある
- 江戸時代からの「蔵」が現存している
地域情報
松本の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]shirakaba:10000483[/rakuten]
[rakuten]ayuwara:10001626[/rakuten]
小浜市
若狭の中央部に位置する小浜は、その昔は国造がおかれ、対岸諸国とはシルクロードの日本の玄関口として交易でも栄えた土地。理的にも近江や京都や奈良に近いため海を利用した商取引は江戸時代になると北前船の拠点ともなる。海の道は同時に文化の伝達の経路にもなり、小浜にも京都や奈良の影響があらわれている。特に東大寺の「お水送り」があるところから、「海のある奈良」とも呼ばれている。
初めてお城を築いたのは武田元光で、江戸時代には京都と縁のある京極家へ所領が移り、海沿いに城郭が築かれる。市内を北川と南川が流れ、その間には、国分寺、多田寺、神宮寺、明通寺の三重塔などの国宝や重文を持つ寺院が、旧鯖街道に沿って在所している。
観光面では、蘇洞門(そとも)と呼ばれる日本海の荒波が作り出した岩の風景を船で眺めるのが観光客に人気。
最近では、森林(もり)の水PR館がオープンして、木製の家具、漆工芸、若狭粘土瓦などの伝統工芸を紹介している。若狭和紙、塗箸、若狭めのうも特産品。
日本海に面していることもあって魚介類が豊富。特にふぐが名物。
福井県の小京都・小浜市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
小浜の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]genkiworld:10011075[/rakuten]
[rakuten]obamaya:10000049[/rakuten]
越前大野
織田信長から大野城主に任じられた金森長近が、京都にならって東西南北に碁盤の目状に整備したのが始まり。時は戦国時代。このころになると、激しかった一向一揆の抵抗もほぼ平定されていた時期になる。天守閣も造られたが、大火で焼失。現在あるのは復元によるもので中は郷土資料館と展望台になっている。
地形的には周囲を千メートル級の山々に囲まれた盆地で、その間を美濃街道が走っていた。
藩主は何度も代わったが、中でも土井利忠は西洋文化に興味を持ち、早くから世界へ目を向けていた藩主だった。また、藩政改革でも辣腕を振るったことから、金森長近とともにお城跡に銅像がある。
名水百選のひとつの”御清水”は観光客にも人気の場所。水環境が優れていることからイトヨの生息地としても知られるようになり、本願清水 イトヨの里といった施設も造られている。これらは、山々に降り積もった雨や雪が地下水となり湧き出たもの。大野の湧き水はお清水(おしょうず)と古くから生活する人々の命だった。
歩いて楽しいのは、古くから碁盤の目状に整備された街並みにお寺が並ぶ寺町。この場所に寺院が集められたのは、もちろん防衛上の意味もあった。
七間通りでは4百年の歴史を持つ「七間朝市」が、春分の日から十二月末まで開かれる。
福井県の小京都・越前大野の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 名刹の「お寺」がある
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
地域情報
越前大野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]auc-yumeikan:10000318[/rakuten]
[rakuten]valumore:10729642[/rakuten]