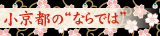山口市
山口市は日本一人口の少ない県庁所在地ですが、室町時代には「西の京」として栄えた歴史を持っています。これは当時、巨大が勢力を持った大内氏が、京都をまねた街づくりをしたことによるもので、鴨川をまねた一の坂川、八坂神社は京都の八坂神社より御神行を仰いでいて、本家京都の祇園祭までが、山口祇園祭として行われています。
また、繁栄の名残は巨大な瑠璃光寺五重塔にも見ることができます。京文化を色濃く繁栄した山口の中にあって、亀山公園には戦国時代に日本にたどり着いた宣教師ザビエルの塔がありますが、これはサビエルが室町時代の京都の衰退に驚き、山口に布教の拠点を求めた縁とされています。当時のザビエルの目には山口こそ、日本の中心のように見えていたのかもしれません。
やがて山口は戦国時代になると急激に勢力を増してきた毛利家に支配が移りますが、毛利家は関ヶ原の合戦で事実上の敗戦となったために防長二州に削封され萩に移ることになります。幕末になると長州藩は弱体化した幕府を無視し、藩庁を萩から山口へ勝手に移し、さらに山口を統幕の拠点としました。その後の明治維新においては多くの指導者を輩出したことは広く知られており、中でも大村益次郎、井上馨が有名です。
近代詩人の中原中也も山口の出身で記念館もあります。
山口県の小京都・山口市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 江戸時代からの「蔵」が現在も現存している
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
山口の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]trv:10004572[/rakuten]
[rakuten]trv:10004574[/rakuten]
竹原市
穏やかな瀬戸内の気候の中にあり、江戸時代へタイムスリップしたかのような街並みが今も残っています。小京都の中でも特に見応えのあるのが安芸の小京都と言われるこの竹原市です。京都・下鴨神社の荘園があった京都縁の地であり、川の名前も加茂川と、京都の影響を色濃く受けていることをうかがわせます。
江戸時代には塩田と酒造により栄えた町民文化の町で、江戸後期から明治初期にかけて造られた家々が、今も当時の姿で町並みとして保存されており、かなりの長さがあるため贅沢な散策になるでしょう。この街並みは長さは、江戸時代に塩田開発で栄えたことを今に伝える歴史の証人t言えます。中でも、大小路、板屋小路、本通り北の町屋の美しさはため息が出るほど。
また、少し高い場所にあるのが、長生寺、西方寺で、こちらからの眺めも素晴らしく訪れる人の心を捉えます。
これだけの町並を保存して維持するのはここの居住する方にとっては制限が多く、大変な苦労があると思われますが、そのおかげで素晴らしい風情に包まれながら通りを歩くことができる素晴らしい街です。特に竹原格子と呼ばれる狭く密になった形の美しさは、一軒一軒に意匠や工夫が凝らされているので、注意して歩いてみるといいでしょう。
竹原出身の頼山陽(らいさんよう)は竹原儒学の祖で、幕末の尊王攘夷思想に影響を与えた人物であり、学問の世界でも町民が中心であったというのが一つの特徴です。
小京都の中でも、おすすめ度はベスト3に入ると言われる程の街です。
広島県の小京都・竹原市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
尾道市
尾道水道のある風景はいつも穏やかで、これほどの落ち着いた風景は他には思い浮かばない。特に高台にある千光寺からの眺めは、安らぎを感じる風景として多くの人を魅了します。瀬戸内に面し、山がすぐ後ろまで迫ってきているため、町並みは細長く、そして坂の町である。古くから多くの文化人に愛され、文学の町としての側面もあるのも尾道の特徴。
志賀直哉、林芙美子、中村憲吉・・・文学の小道と名付けられた散策路には、たくさんの文学碑が並んでいます。また、画家の梅原龍三郎宅を復元した尾道白樺美術館も雰囲気のある場所。
最近では、尾道出身の大林宣彦作品により、映画として知名度が急上昇中です。尾道三部作(転校生、時をかける少女、さびしんぼう)、新尾道三部作(ふたり、あした、あの、夏の日)は尾道を舞台として撮影されたもので、まるで尾道市全体が大林映画のオープンセットであるかのよう。
これらの詳しいデータは、おのみち映画資料館でも見ることができます。
四国と橋によって結んだ「しまなみ海道」により、数年前からは駅前の開発が大きく進み、古きよき時代の面影は少なくなりましたが、ちょっとだけ町の中に入れば、いつもの坂の町の風景が迎えてくれる。
揺れる電車の窓から日立造船の大きな看板を見えると「ああ、また尾道へ来たぞ」と心が高鳴る町です。
広島県の小京都・尾道市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
尾道の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]sankin-asaichi:10007251[/rakuten]
[rakuten]onomichi:10001395[/rakuten]
高梁市
美観地区の紺屋川筋、庭園の素晴らしい頼久寺は特に見応えがある。
江戸時代は水運を利用して発達した町で、タバコの産地である。つい最近までJTの工場もあった。
盆地の中にあり、高梁川が昔のたたずまいを残す町を静かに流れている。
鎌倉時代に臥牛山に砦が築かれたのが、城下町としての始まりになる。
天守閣のあるお城としては日本一高い場所にある備中松山城が町の自慢だが、このお城は江戸時代の城主・水谷勝宗による改修によるもので、ほぼ当時の姿を残している。
庭園が美しい頼久寺は足利尊氏の建立したもの。
美観地区の紺屋川筋、城下町らしく武家屋敷沿いの道は、気持ちのいい散策路になっている。
見所はいろいろあるが、古いモノなら何でも並べたような郷土資料館が、庶民の生活様式などがわかって面白く勉強にもある。
武家屋敷は二百石程度の侍の屋敷だったもの、醤油の製造場でもあった商家資料館もある。
「童謡のまちづくり」を目指しており、近くに立つと歌い出すブロンズ像が市内に何カ所かある。
一番のお祭りは、備中松山踊り。
「映画のロケ地」を示す看板がよくある町だ。
岡山県の小京都・高梁市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 名刹の「お寺」がある
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
高梁の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]tennindo:10000010[/rakuten]
[rakuten]book:12594633[/rakuten]
津山市
古くは美作国府・国分寺が置かれた政治・経済の中心にあり、旧出雲街道の要衝として栄えた。街道沿いに歩くと古い町並みが残っている津山。防衛上の拠点として配置された寺院もよく今日まで残っている。津山盆地の中を吉井川が流れ、水運を利用して高瀬船も往来していた。
江戸時代の二代藩主の森長継が京都から作庭師を招集して、仙洞御所をまねて造園させたのが衆楽園。長い池に四つの島を配置し、中国山地を借景した名勝として知られる。城跡には天守閣などはないが、鋭い石垣が鶴山公園として残っており、名城らしい面影を見ることができる。特に桜の季節になると美しい姿を見せる。
室町時代にもお城はあったが、応仁の乱の余波で廃城となり、本格的に築城されたのは江戸時代に入ってからである。この地を治めた森家は、本能寺の変で織田信長とともに討ち死にした森蘭丸に繋がり、お城も弟忠政が築城したもの。江戸時代に入ると松平家が変わって入城し外様大名を卒業した。
市内は武家屋敷町、町人町、商人町と分かれていた地域が、今も面影を少し残している。中でも城東地区一帯がよく残っており、小路も歩いていても楽しい。
岡山県の小京都・津山市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
地域情報
高梁の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]milkycorn:10000368[/rakuten]
[rakuten]es-toys:10226224[/rakuten]
津和野町
津和野は、掘割や白壁のある風情溢れる町並みが残る津和野は、文学・芸術家が生まれている。
盆地の中を整備された津和野川が流れ、鉄道と国道も平行して通っている。
津和野城は元寇に備えて三本松城として築かれたもの。以後歴代藩主の居城となる明治まで城下町として続く。現在は石垣だけが残り、遠くから見上げると形がわかる。
鎌倉時代の吉見氏、戦国時代の崎坂氏、そして江戸時代に入ってからの亀井氏と続く城下町で、町内には城下の雰囲気が残っている。
特に殿町は土塀の落ち着いた町並みに、鯉の泳ぐ姿を見ることができる。掘割を優雅に泳ぐ鯉だが、始まりは飢饉に備えて食用の魚を養殖していたものだ。
城下町だったため、藩校だった養老館跡や家老門が残っていて見学もできる。
文豪・森鴎外の出身地で、十一歳まで過ごした旧宅が現存するほか、記念館も造られている。なお、お墓は歴代藩主の菩提寺でもある永明寺にある。
現在、新しく最も人気のある観光スポットが「安野光雅美術館」。津和野出身で世界的に評価の高い絵本作家の個人美術館になっており、原画も常設展示の他、特別展示が行われている(私が訪れたときは「平家物語」が展示されており、素晴らしい作品をみることができた)。建物は蔵風で、昔ながらの小学校の教室も再現されていて面白い。
島根県の小京都・津和野町の観光ポイント
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
津和野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]whitecalle:10004945[/rakuten]
[rakuten]neowing-r:10389776[/rakuten]
松江市
宍道湖に面した松江の風景はここにしかないものだ。特に松江城の天守閣に立って眺めると湖が海のように見えるためその感が強い。日本を代表する平城である「松江城」を築いたのは堀尾吉晴で、その後は松平家が十代に渡って松江を治めている。特に七代藩主の松平治郷(不昧公)は茶人としても有名で、当時の茶室の明明庵も保存公開されている。お堀に沿って武家屋敷の塀が並ぶ通りを、家老の塩見家の屋敷があったことから塩見縄手と呼んでいる。
後に「知られざる日本の面影」など数々の作品で日本を紹介した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、松江で英語の教鞭を取っていたころに過ごした家(元々は武家屋敷)が記念館と隣り合わせて立っている。
小泉八雲は日本では、怪談の作者として有名だが、国際的には日本の研究家として知られていた。
市内から少しだけ離れたところにある松江しんじ湖温泉は人気の温泉。
また、松江は古代出雲文化圏の中心地でもあったため、市内には山代二子塚、神魂神社などの古墳古社がある。律令時代の出雲国庁もこの地にあった。
遊覧船に乗っての堀川めぐりが観光客には人気。
島根県の小京都・松江市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」(当時の天守閣がある)
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
松江の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]sanintoretatehonpo:10000814[/rakuten]
[rakuten]joshin-cddvd:10151599[/rakuten]
倉吉市
奈良時代には伯耆国分寺や国庁が置かれていた歴史のある倉吉は、南北朝、室町期を通じて城下町として栄え、江戸時代になると商業の町となった。ただ、お城は、江戸幕府初期に定められた一国一城令により廃止になっている。
室町期創建の長谷寺から玉川沿いに並ぶ江戸期の商家の街並みや白壁と黒い焼杉の土蔵群、古い蔵を改造してつくられた「赤瓦」が雰囲気のある通りを作っている。
最近では、工場跡地に「倉吉パークスクエア」がオープンし、中でも「鳥取二十世紀梨記念館」が人気を集めている。鳥取は梨が、特に二十世紀梨が特産なのだ。
廃線となった倉吉線の跡地には「緑の彫刻プロムナード」として彫刻が作られ、小さいながらも倉吉鉄道記念館が途中にある。(現在の最寄駅は倉吉駅だが、市内中心部までは距離がある)
市内を一望できる打吹公園は室町時代はお城のあった場所だが、平成十六年に開園百周年を迎える。
はこた人形は、江戸時代から伝わる張り子の人形で、工房では制作過程を見学することも出来る。
公衆トイレの整備にも力を入れていることでも有名で、凝ったデザイントイレが幾つもあった。
なお、滝沢馬琴の南総里見八犬伝のモデルと伝えられる里見安房守忠義と八人の家臣の墓所も市内の大岳院にある。
鳥取県の小京都・倉吉市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 名刹の「お寺」がある
- 江戸時代からの「蔵」が現存している
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
倉吉の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]iimonotottori:10000300[/rakuten]
[rakuten]aikuru:10088931[/rakuten]
龍野市
「夕焼け小焼けの赤とんぼ」で知られる三木露風の出身地で、他にも内海青潮、矢野勘冶、三木清などの文学者を排出している。龍野公園には「哲学の小径」「文学の小径」「童謡の小径」がある。特に「赤とんぼ」が著名なことから、龍野は「童謡の里」と呼ばれている。市内に童謡の碑や「赤とんぼ」に関連する施設や名称を見るのもそのためだ。
江戸時代に龍野を収めていた脇坂藩は外様大名ではあったが、老中を排出している。
始祖は豊臣秀吉の側近で柴田勝家との戦いで賤ヶ岳七本槍のひとりとして名をあげた脇坂安治となる。
武者行列のお祭りが当時を偲ぶ。また、同藩は忠臣蔵の中で、取りつぶされた赤穂城の受け取り藩としても記録が残っている。お城には天守閣はないが、多門櫓や埋門が復元されいる。跡には歴史文化博物館になっており、市内の白壁や瓦屋の並ぶ市内、醤油工場を望むことができる。
武家屋敷は跡だけが残っている。
うすくち醤油と手延べそうめんが龍野の名産。町を歩けば醤油倉の姿があり、うすくち龍野醤油資料館もある。特に上方で人気があり京料理に重宝された。これも龍野がに清水があったことによる。
市内を流れる川には高瀬船が往来していたと伝えられている。
兵庫県の小京都・龍野市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 町人文化が息づく
地域情報
龍野の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]japan-ds:10058018[/rakuten]
[rakuten]bansyumen:10000060[/rakuten]
篠山市
徳川家康により西国の見張りとして築城されたのが篠山城。多紀連山に囲まれた盆地の篠山が歴史の重要拠点となるのは関ヶ原の合戦の直後である。勝利した徳川家康は大坂城を本拠とする豊臣政権を包囲する城のひとつとして、また豊臣家の影響力を持った西国大名との抑えとして、篠山城を築城した。城主に家康が実子の松平康重を充てたことからも、この地の戦略的な重要性がわかるだろう。築城は、縄張の名手といわれた藤堂高虎による堅固なもので、わずか半年で完成にこぎ着けたと伝えられている。現在はニの丸に復元された篠山城大書院があるが、これは迫力があり見応えのあるもの。元々は1609年(慶長14年)の築城と同時に建てられたが1944年に焼失。大書院は、それを忠実に復元したもの。なお、篠山城にはそもそも天守閣が築かれていない。
藩政時代には能が盛んになり、春日神社には能楽堂が残っており、今も奉納されている。
現在の篠山市は、1999年に多紀郡の四町が合併して誕生した市。
デカンショ節はこの篠山が発祥の地で、八月にはデカンショ祭が開催されている。
兵庫県の小京都・篠山市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
篠山の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]kikumasa:10000071[/rakuten]
[rakuten]1megumi:10000009[/rakuten]