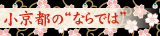日南市飫肥
江戸時代には五万一千石・伊東家の城下町だった飫肥は、盆地の中に昔ながらの石垣や土塀のある武家屋敷や藩学校を今も見ることができます。町の通りは二色のような街並みで、飫肥街道の本町商人通りは、新しい道路の両側には白壁や瓦屋根の家並みが続き、歩いていて気持ちのいい道なっており、今日の商店街の中にも昔ながらの色彩を残しています。案内板にも特産の飫肥杉を使われています。お城跡の背には男鈴山と小松山があり、迂回するように酒谷川が流れています。
小村寿太郎生の出身地で記念館もあり、鯉の遊泳でも有名です。
同じ日南市の中でも、中心部から離れたこの「飫肥」は、江戸時代には伊東氏が治めた城下町でした。復元された大手門と城跡の中には「松尾の丸」「豫章館と庭園」「歴史資料館」「小村記念館」といった見所があります。近くには武家屋敷跡もあるが、今も個人宅として実際に生活に利用されているため公開されていません。
食の名物はなんといっても「おび天」で、これは魚の摺り身に豆腐、黒砂糖、味噌などを練って固めた揚げ物でほのかな甘みがあるのが特徴です。
宮崎県の小京都・日南市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
飫肥の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]syurui:10009032[/rakuten]
[rakuten]kaioo-sake:10003695[/rakuten]
日田市
日田市は、戦国時代には豊臣秀吉が、江戸時代には幕府が直轄の天領として栄えた歴史を持つ歴史の町で、天領時代のひな人形や書画などは、この地の持つ歴史の奥深さを感じさせてくれます。
また、水郷の里であり「水郷日田」とも呼ばれ、三隈川と花月川が市内を流れます。九州の各地に移動することのできる水運の中心地でした。水がきれいなため、現在ではサッポロビール新九州工場を日田市に操業しました。
儒学者の広瀬淡窓(ひろせたんそう)が開いた身分、能力を問わずに入門することができる私塾・咸宜園(かんぎえん)が重要文化財として残っています。当時は全国から門弟が集まったといわれています。
歩いて楽しいのは豆田町で、決して江戸時代のものではないものの、雰囲気のある通りになっています。
鵜飼、下駄の産地、温泉の町としても有名であり、七月の末にある日田祗園山鉾のお祭りなど江戸の栄華を彷彿させる日田市には風情のあるお祭りが多く受け継がれています。
巨大な近代的な観光施設はないものの、逆に小さいながらも貴重な資料館などが多く、特に江戸時代は一部の大金持ちしか手にすることのできなかった高価な「おひな様」が各所で見ることができます。
大分県の小京都・日田市の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
日田の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]misono-support:10002847[/rakuten]
[rakuten]seijoishii:10003580[/rakuten]
人吉市
人吉市は桐木の胴体に、松を輪切りして作った車輪をふたつ取り付けた伝統工芸品でも有名な熊本の小京都です。古くからきじ馬と呼ばれ、平家の落人が京都で培った技術を用いて始めたと伝わっています。わずかながら人吉に京の文化の感じられるのは、平家の落人によるものと伝えられており、歴史のロマンを感じることができます。きじ馬以外にも人吉には工芸品が多く、それらは人吉クラフトパーク石野公園で実際に制作行程が体験ができます。
人吉の歴史は以外と古く、相良氏による統治が、鎌倉時代から幕末(江戸時代は二万二千石)までの長きに渡って続いきました。歴史ある建造物は、西南戦争でそのほとんどが焼け落ちたため、当時の面影を残すのはわずかですが、武家屋敷だった武家蔵、伝承蔵、みそ・しょうゆ蔵などは今でも見ることができます。これらの蔵は、元来は防塞の代わりのものだったようです。
市内には日本三大急流の一つに数えられる球磨川が流れており、奇岩、怪岩の間でスリルが味わえる、川下りとして県内外から多くの観光客が訪れています。タイミングがよければ、人吉橋の上から「くま川下り」に出かける船を見ることができます。
城下町として栄えた人吉だが、お城跡は今では公園になっており、その本丸跡地に市役所があります。その西北部石垣の上には角櫓、長塀、多門櫓が復元されていて当時を忍ばせてくれます。
熊本県の小京都・人吉市の観光ポイント
- 時代を超えて「武家屋敷(武家蔵)」が残る
- 江戸時代からの「蔵」が現存している
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
人吉の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]kuma-shochu:10000001[/rakuten]
[rakuten]bussankan:10000106[/rakuten]
伊万里市
江戸時代にはヨーロッパまで積み出され、海の向こうの王侯貴族を魅了した色絵磁器焼き物の産地。四百年の歴史があり、特に格調高い高級品を生み出し名声を高めました。
伊万里焼とは元々は有田焼きで、技術流出を恐れた鍋島藩が、藩御用窯を伊万里の大川内川へ作ったのが始まりとされています。その昔は、豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄・慶長の役)により渡来した李氏朝鮮の陶工が十六世紀に掛けて唐津焼に原点ともいえる磁器を作成したものです。
伝統の陶磁器は、町を歩けば巨大な壺や人形として日欧の影響を受けたモニュメントや像の形であちらこちらで見ることができます。
壺元が集まる(集められた)大川内川の山間にレンガの煙突が並ぶ風景はここだけのもので、焼き物を体験できる壺元もあります。春には「春の窯元市」が、 秋には「鍋島藩窯秋祭り」が、10月には日本三大喧嘩祭りの「トンテントン」が開催されています。トンテントンは日本三大喧嘩祭りに数えられるほどの激しいお祭りです。
最近では、映画監督の「黒澤明記念館サテライトスタジオ」がオープンしたことでも話題になりました。
古くから貿易港であり、元寇の頃のは松浦水軍の拠点、その後は伊万里焼の積出港、近代に入ってからは石炭産業全盛期は石炭の積出港として栄え、今日を迎えています。
佐賀県の小京都・伊万里市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 江戸時代からの「豪商の面影」を見ることができる
- 町人文化が息づく
地域情報
伊万里の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]b-miyoshi:10000740[/rakuten]
[rakuten]comingimari:10001028[/rakuten]
小城市
天山山系の穏やかな山並みが見える、清流と花とホタルの町、小城市。
鎌倉幕府成立の恩賞としてこの地に地頭として関東から入ったのが千葉氏で、中でも千葉介胤貞が、下総から小城へ赴任してからは、京都の祇園社(八坂神社)の分霊を千葉城の一郭に置き、京都に似た街並みを作り始めました。京都を彷彿させる清水川と祗園川(清水川の支流)が今も流れています。
山曳祇園は六百年の歴史があり、江戸時代になるとさらに賑わい「見事みるには博多の祇園、人間みるなら小城の祇園」とまで言われるほどでした。
見所の一つである小城公園は、江戸時代に入ってからの初代藩主である鍋島元茂から二代藩主直能によって造られた名庭園で、桜の名所、つつじの名所として地元の人々に親しまれています。また、小城は源氏ボタルの名所であり、祇園川で見ることができます。
石造の五百羅漢がある星巖寺は小城藩主の菩提寺として有名です。
佐賀県の小京都・小城市の観光ポイント
- 「桜の名所」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
小城の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]shinpudo:10000544[/rakuten]
[rakuten]youkanya:10000041[/rakuten]
甘木市
福岡県のほぼ中央部に位置する甘木市は甘木秋月とも呼ばれる九州の小京都です。「古処山」を背に筑後川が市内を流れ、黒田支藩五万石の城下町で周囲は伝統的建造物群保存地区に指定されています。秋月の地名は、鎌倉時代に秋月氏によって開かれたことによるもので、豊臣秀吉による九州平定後には、戦国武将の黒田長政の三男、長興が秋月家の領土を受け継ぎました。当時に築城されたのが秋月城ですが天守閣は当初よりありませんでした。当時の面影は少ないものの、わずかに残る武家屋敷や商家にその時代の面影を見ることができます。また、黒田藩の名残として、林流抱え大筒(火縄銃)、光月流太古が伝えられています。
維新直後の明治九年には、不満士族らによる「秋月の乱」が起き、二百五十人による秋月党が決起するが政府軍の小倉連隊に敗れるという事件が勃発しました。これは西南戦争の四ヶ月前のことです。
甘木市は、美しい川と豊かな緑により、ホタルと淡水魚の名所となっています。水を限りある自然と位置づけて重要性を静かに伝えてくれる「あまぎ水の文化村」、ビール工場の「キリンビアファーム」も観光客に人気のスポットです。
九州の歴史ある土地らしく、邪馬台国伝説の元になった「平塚川添遺跡」をはじめ古代遺跡が点在し、弥生時代から古墳時代の集落や墓などの遺跡も多く、各時代のものが満遍なく出土することでも知られています。
福岡県の小京都・甘木市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 「桜の名所」がある
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
甘木朝倉の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]fugetsu-f:10000010[/rakuten]
[rakuten]jathikuzenasakura:10000250[/rakuten]
中村市
中村市は、元々応仁の乱により京から逃げてきた関白一条教房が、京都を模して碁盤の目上の町を造ったことに始まります。残念ながら、太平洋に面しているため、その後の台風、水害や地震などの災害により当時の面影を見ることはできませんが、日本最後の清流・四万十川の河口にあり、開発が進む日本の中で、自然を体験できる貴重な地域です。九十種類もの魚が生息することから川魚の宝庫と呼ばれる四万十川には多くの伝統漁法が伝えられ、川によってもたらされた文化や四季折々の祭りが残り、様々ば催し物が行われています。他にも、湿地帯を整備したトンボの生息地があり、野鳥自然公園があり、海ではホエールウォッチングが楽しめます。
一条教房が再び京都へ登る夢は果たせなかったものの、大文字の送り火や京都らしい地名が現在も残っています。それらの歴史は中村城跡にある天守閣風の資料館で学ぶことができます(お城にこのような天守閣があった歴史はありません)。
明治四十四年の大逆事件で処刑された社会主義者の幸徳秋水の出身地であるため、関係石碑なども多く存在します。
四万十川学遊館、四万十いやしの里、四万十川野鳥公園などもあり、さらに、郊外へ行くと、川の流量が増えて沈下することを覚悟して作られた沈下橋を見ることができます。
高知県の小京都・中村の観光ポイント
- 名刹の「お寺」がある
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
地域情報
四万十市の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]chokuhan:10031984[/rakuten]
[rakuten]ayuwara:10001588[/rakuten]
安芸市
小京都というより阪神タイガースのキャンプ地として有名かもしれない四国の安芸。市内にはタイガースタウンの文字があるほどです。
安芸の地名は十六世紀までこの地帯を支配していた安芸氏に由来します。戦国時代は長曽我部一族、江戸時代になると土佐藩主になった山内一豊が納めた土地であり、安芸には家老の五藤家が入り、当時の武家屋敷は土居廓中と呼ばれて今も残っています。同じく江戸期の建物である岡御殿は豪商の屋敷だったものです。
安芸は三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎や童謡の作曲家である弘田龍太郎も輩出しています。童謡が刻まれた曲碑が市内の各所に作られ、童謡の町を目指しているのもその所縁です。
町のシンボル的な存在になっているのが、明治時代にすべてを手作りによって作られた野良時計と呼ばれるもので、百十年に渡って旧家の屋根で時を刻んでいます。この野良時計は安芸城跡に近く、周辺には武家屋敷や歴史民族資料館などの見所が集まっているため散策のしやすさもおすすめポイントです。
残念ながら廃線になった旧国鉄の線路が、再び形を変えて土佐くろしお鉄道として開設され高知などと結ばれています。これまでは高知からのバスに頼っていたため観光客にも(タイガースファンにも)大変便利になりました。
高知県の小京都・安芸市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 町人文化が息づく
地域情報
安芸の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]takahashiya:10001041[/rakuten]
[rakuten]hanafusa87230:10001234[/rakuten]
大洲市
加藤家が治めた伊予大洲六万石の城下町である大洲は、盆地の中に肱川が流れる水郷の町としても広く知られています。鵜飼いはこの地方の風物詩となっており、川に沿って船がむすばれている姿を見ることができます。
大洲の歴史は鎌倉時代にまで遡ることができ、伊予守護職により城が築かれていました。さらに、それ以前の古代文化の巨石遺跡が残っています。江戸時代に入ると本格的に栄え、当時の蔵屋敷や商家、レンガ造りの建物が今も多く残っています。臥龍山荘の庭園は藩主の清遊地だったもので、凝った建築様式の建物、肱川の眺めなど見所の多い小京都です。
年輩者の方は記憶にあるかもしれませんが、市内に入るとよく聞く「おはなはん通り」は、NHKの朝の連続ドラマのロケ地になった昔ながらの町並みが残っている通りのことです。
土色の壁面を持つ蔵屋敷が並んでいてタイムスリップしたような感覚を覚える人も多いとか。
大洲城は歴史に基づいて正確な復元を目指したもので、従来からあった高欄櫓、台所櫓などと結んで天守群を形成します。コンクリートにより復元されている他のお城とは違う貴重なお城です。。
名物は鍋にサトイモや鶏肉を煮て食べる「いもたき」が有名です。
愛媛県の小京都・大洲市の観光ポイント
- 江戸時代からの「城下町」
- 京都ゆかりの「寺院」がある
- 京都の影響を受けた伝統の「お祭り」が今も続く
- 町人文化が息づく
地域情報
大洲の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]shop-takeichi:10000232[/rakuten]
[rakuten]gintengai:10003185[/rakuten]
萩市
関ヶ原の合戦において西軍側にいた毛利家は徳川家康によって山口の領土を取り上げられ、移った場所がこの萩です。それから二百五十年を経て、明治維新の際には多くの維新の獅子を輩出し、彼らは日本の近代化に努めました。そのため、市内のあちこちに銅像が立ち、歴史的人物の縁の地があります。中でも、特に指導的な役割を果たした吉田松陰の松下村塾は、松陰神社の境内に残されていて、季節を問わず多くの観光客で賑わっています。
武家屋敷地区では、映画撮影用のセットのように高杉晋作、田中義一、木戸孝允の旧宅が並ぶ様はまさに壮観。武家屋敷が残る小京都は多いですが、これだけの歴史の偉人が並ぶのは萩ならではのことです。これらの武家屋敷の塀が美しく映えるのは五月の初旬、夏みかんのある景色です。元々は、生活に苦しむ下級武士を救済するために始まった夏みかんの栽培が、今も武家屋敷の塀の上から実を付けている様子を見ることができます。
萩の町は、天然の要塞のように萩城島が日本海と橋本川、そして運河に囲まれており、また、鍵曲(かいまがり)と呼ばれる敵軍の進路を妨害する見通しのきかない屈折して曲がる道路を見ることができます。
山口県の小京都・萩市の観光ポイント
- 「女性に人気」の観光地
- 江戸時代からの「城下町」
- 時代を超えて「武家屋敷」が残る
地域情報
萩の名産品・お土産お取り寄せ
[rakuten]umemotoshoji:10000002[/rakuten]
[rakuten]ms-machi:10012211[/rakuten]